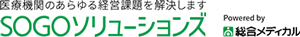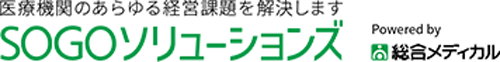事例紹介
横浜市の基幹病院の「食生活で病気を予防する」想いを病院レストランがメニュー開発から支援

横浜市立市民病院
所在地:横浜市神奈川区三ツ沢西町1番1号
電話:045-316-4580
URL:https://yokohama-shiminhosp.jp/index.html
病床数:650床、集中治療室(ICU・CCU)18床、救命救急病棟(HCU)24床、新生児集中治療室(NICU)9床、新生児治療回復室(GCU)6床、緩和ケア病棟 25床、感染症病床 26床
診療科目:診療科(34科)、標榜科(32科)、腎臓内科、糖尿病リウマチ内科、血液内科、腫瘍内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、消化器外科、炎症性腸疾患(IBD)科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、救急脳神経外科、脳血管内治療科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、神経精神科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、感染症内科、病理診断科、救急診療科、緩和ケア内科
課題
- 医療機関として健康的な食事の啓発や提案を行いたいと構想していた
- 中高年の筋力低下や骨粗鬆症を予防する食事メニューを作りたかった
- 患者さんや職員、地域の人々に健康的な食事を提供できる場所が必要
- 職員の健康と満足度を高め、福利厚生面からも食堂機能を強化したい
- レストラン単体では持続可能な運営が難しい面があった
解決策
- 文教とともにメタボ対策、高血圧対策、骨粗鬆症予防に配慮したメニューを開発
- 朝早くから夜遅くまでレストラン・カフェ・コンビニが利用できるようにした
- カフェやレストランの窓から公園が見える座席配置をするなど環境づくりに配慮
- レストラン・カフェ・コンビニの統合的な運用を可能にした
効果
- 開発した骨粗鬆症予防メニュー「骨ランチ」は毎月120~160食と好評
- 利用時間の拡大、メニュー増強により、職員の満足度が向上した
- 三ツ沢公園の利用者が訪れる地域につながるレストランが実現できた
- レストランの持続的な運営が可能となり、福利厚生の一環として定着した
高度急性期医療と政策的医療を担う横浜エリアの中核病院

病院長 中澤 明尋 様
――まず「横浜市立市民病院」がどのような病院か教えてください。
中澤様(以下、中澤):
横浜市立市民病院は、横浜市が直営する市立病院です。当院は、災害拠点病院としての役割、感染症指定医療機関としての機能を持ち、高度急性期医療と周産期医療など、政策的医療と呼ばれる市民のための医療を提供する役割を担っています。特に力を入れているのが、災害医療です。2020年に神奈川区三ツ沢公園隣接地へ移転する際には、大規模災害発生時にも市民の皆さんへ継続して医療提供できるよう、立地や施設整備などを重要視しました。
また、神奈川県内で唯一の第1種感染症指定医療機関である点も特徴です。新型インフルエンザやエボラ出血熱などの感染症が発生した場合、まず当院で患者を受け入れることになっています。2020年2月、横浜へ入港したクルーズ船で確認された日本国内初めての新型コロナウイルス感染症患者を当院で受け入れました。

周産期医療も重要な役割の1つとして、山中横浜市長が掲げる「安心して出産、子育てができる横浜市」という政策を医療面から支えています。年間約1,200件の出産を担うほか、子どもの夜間救急医療も担当し、小さなお子さんの総合診療を24時間体制で提供しています。
当院は、病院の規模拡大に伴うスペース不足や老朽化による機能低下の課題を受け、5年前に新病院へ移転しました。近年の物価と建築コストの高騰を踏まえると、適切なタイミングでの移転であったと考えています。現在は、医師・看護師などを合わせて約1,600名のスタッフと、34の診療科、650床の規模で運営しています。
災害時の対応力など幅広い提案を評価し、総合的なサービス導入を決定

――移転前の2017年にレストラン事業や売店、入院セットを文教に委託した当時の背景にはどのようなことがあったのでしょうか?
中澤:
旧病院にもレストランや売店がありましたが、移転にあたって患者さんと職員の双方が利用できるレストラン、カフェ、コンビニを統合的に運営してくれる事業者を公募することにしました。
文教に決定したのは、レストラン単体での運営が厳しいという課題があるなか、コンビニや売店を含む総合的なサービス提供と採算性のバランスを考慮した提案があったためです。大規模災害発生時に患者さんや避難者、職員への食事提供が可能であることや、医療材料などの物流ルートを確保できることなど、災害対応に関する提案が充実していた点が決め手になりました。また、レストランの営業時間の長さも評価したポイントです。
新病院では災害拠点病院として停電・断水等でも一週間は自立できる設備(貯水槽や自家発電機)等を持っています。大規模災害時には多くの避難者を受け入れることになるでしょう。そうした時にレストランやコンビニからも協力いただけることは、市民の最後の砦としての機能を強化してくれると期待しています。
レストランを患者さんや職員の健康に貢献する場にしたい

――病院が移転した2020年5月にオープンしたレストラン「B’EASE(ビーズ)」では当初から健康を意識したメニューだったのでしょうか?
中澤:
意識していました。移転前から「病院内レストランを単なる食事提供の場ではなく、患者さんや職員の健康に貢献する場にしたい」という構想を持っていました。
以前視察した九州地方の病院で、多彩で美味しく健康的なランチが提供されていたことに刺激を受けました。当院は運動公園として知られる三ツ沢公園に隣接しており、利便施設棟は病院利用者以外も自由に出入りできるようになっています。そのため、市民が公園で運動した後にレストランで健康的なランチが食べられるような、地域の健康増進の拠点にしたいと考えていました。
私自身、整形外科医として骨折の治療に携わってきた経験から、高齢者の健康維持に食生活が深く関わることを強く認識しています。特に、骨粗鬆症やフレイル・ロコモの予防に食事が果たす役割の重要性は計り知れません。当院では、「フレイル・ロコモ骨粗鬆症検診」を開始するとともに、文教と相談し、骨粗鬆症予防に効果的な栄養素を含んだメニューの開発を始めました。
健康志向で評価されているタニタ食堂のように、病院のレストランで食事をすることが、健康増進につながるような理想的な食環境を目指しています。
――メニュー開発にあたり、味の面などで文教にリクエストされたことはありましたか?

骨粗鬆症予防に役立つ栄養素を多く含んだ「骨ランチ」
中澤:
私たちが医療機関として伝えたいのは、どのような食材にどのような栄養素が含まれ、それが健康にどう貢献するかという情報です。
現在レストランでは、日本人に不足しがちなビタミンDを豊富に含むキクラゲを使用した「骨ランチ」を提供しています。ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨粗鬆症予防に役立つ栄養素であることを、食事を通じて皆さんに理解していただきたいという考えから、メニューのリクエストに至りました。
文教はキクラゲを中華風に調理することで、美味しくビタミンDが摂取できるメニューを開発してくれました。当初は患者さん向けのメニューとしての考案でしたが、実際には付き添いの方々にも利用いただき、月に120~160食もの注文がある人気メニューとなっています。
病院は、病気の治療だけでなく、予防に貢献するための場所でもあります。予防医療の一環として、「骨ランチ」のようなメニューを通じて多くの方に健康的な食事の大切さを実感していただきたいと考えています。
――職員の方々の健康も考えて、メニュー展開を考えておられるのでしょうか?
中澤:
もちろんです。職員が安く、美味しく、そして健康的な食事をとり、当院で長く働ける環境を整えたいとの思いから、職員向けのレストランも非常に大切だと考えています。職場環境を良くすることは大事ですが、食の満足度を上げることも福利厚生の観点から重要なことだと認識しています。
健康志向のメニューを発信する病院レストランを超えた存在へ

レストランとカフェに三ツ沢公園を一望できる席を用意
――今後、文教と院内レストラン「B’EASE」に期待していることを教えてください。
中澤:
病院レストランを超えた存在になってもらいたいです。例えば、三ツ沢公園で散歩をした際に、病院のレストランで食事をする人が増えたり、美味しく健康的なものが食べられる「三ツ沢公園のレストラン」として認知されたりと、多くの人に利用していただく場になることを期待しています。
また、メニューのレシピを公開することも要望しています。食材にどのような栄養素が含まれ、それがどのように健康に貢献するのかという情報を広く伝えたいと考えているからです。何のために何を食べるかを理解していただくために、健康に良いレシピの提供が効果的だと思います。これからも市民の健康を予防的観点から守る取り組みの一環として、文教とともに進めていきたいです。