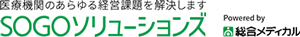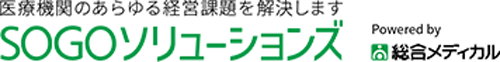コラム
医療現場におけるペイシェントハラスメントとは? 事例や対策を解説
公開日:2024/12/26

近年、医療・介護現場における暴力が取り沙汰されるケースが増えています。医療従事者による暴力事案が報道されやすい傾向がある一方で、患者から医療従事者へ向けた「ペイシェントハラスメント」と呼ばれるケースもあります。医療現場における暴力・ハラスメント対策は、医療従事者の離職防止や勤務環境改善の観点からも重要視されているのが現状です。
とはいえ、ペイシェントハラスメントに対して、どのように対策すべきかお悩みの方もいるでしょう。本記事では、想定されるハラスメント事例と、医療機関が実践できるハラスメント対策をご紹介します。
医療現場におけるペイシェントハラスメントとは
ペイシェントハラスメントとは、医療従事者が、患者やそのご家族などから暴言・暴力などの迷惑行為を受けることを指します。
461名の医師が回答したあるアンケート※によると「診察中にペイシェントハラスメントを受けたことがある」と答えた医師は約7割に上りました。
どのようなハラスメントを受けたかについて「暴言、怒鳴るなど言葉によるもの」、「居座り行為」、「殴る、物を投げるなど身体的なもの」などの回答が挙がりました。また、どんな内容に対してハラスメントを受けたかという設問には、「治療方針・内容」、「医師の言動」、「待ち時間」、「診断・検査結果」などを回答する人が多くなっています。
被害を受けた医師のなかには「身の危険を感じた」と回答する人もおり、ペイシェントハラスメントが医療現場を脅かす深刻な問題であることがわかります。
※株式会社エムステージ「『ペイシェントハラスメント』に関するアンケート」
- 調査対象:株式会社エムステージが運営する『Dr.転職なび』『Dr.アルなび』に登録する会員医師
- 調査日:2023年11月14日~11月28日
- 調査方法:webアンケート
- 有効回答数:461
ペイシェントハラスメントの種類
ペイシェントハラスメントは、医療機関の顧客ともいえる患者による迷惑行為のことですが、一般企業などでも「カスタマーハラスメント」が深刻化しています。ここでは、医療現場でも参考にできるカスタマーハラスメントの種類をご紹介します。
- 時間拘束型:長時間にわたり「居座る」「電話し続ける」といった行為をする。
- リピート型:理不尽な要望などについて「繰り返し電話で問い合わせをする」「面会を求める」といった行為をする。
- 暴言型:「馬鹿」「役立たず」といった暴言を吐き、人格否定や名誉毀損をする。
- 暴力型:「蹴る」「殴る」「ものを投げつける」など、暴力をふるう。
- 威嚇・脅迫型:「殺すぞ」といった脅迫的な発言をする、反社会的勢力との関係性をほのめかす。
- セクシュアルハラスメント型:スタッフの身体を触る、性的な内容の発言をする。
たとえば医療現場では、「待ち時間が長いことに腹を立てた患者が、その場にいた医療従事者に殴りかかる(暴力型)」といった例や「医師の説明に納得がいかない患者や家族が、医師に対して『研修医のくせに』『死ね』などと怒鳴る(暴言型)」、「患者が特定の事務員を指定して何度も電話をかけ、セクハラまがいの言動や理不尽な要求をする(時間拘束型・セクシュアルハラスメント型)」などの例が想定されます。
ペイシェントハラスメントの対策
こうしたペイシェントハラスメントに対し、医療機関は何ができるのでしょうか。ここからは、病院などの医療機関が実践できるペイシェントハラスメントの対策の例をご紹介していきましょう。
対応マニュアルを策定する
これまで院内で起きた事案などを考慮し、患者が引き起こすハラスメントを想定して、対応マニュアルを作っておくことが重要です。
たとえば、患者が院内スタッフに対して殴りかかってきた場合の対応例として、以下のマニュアルを策定することが考えられます。
- まずは患者と一定の距離をとり、身の安全を確保する
- 他のスタッフや警備員などと連携をとりながら、直ちに警察へ通報する
「殴る」「つかみかかる」「暴れる」といった暴力型のハラスメントの場合、院内スタッフだけでなく、ほかの患者にも危害が加わる可能性があります。ただ、危険だとわかってはいても、どのように行動したらよいかの指針がなければとっさの判断ができず、被害が広がってしまうことも。医療機関にいるすべての人の安全が確保できるよう、あらかじめ想定されるハラスメントを洗い出し、適切な対応例を策定することから始めましょう。
院内研修を実施する
対応マニュアルを作成したら、それを周知する院内研修などの機会を設けましょう。患者からの迷惑行為や悪質なクレームに対応できるようにすることはもちろん、患者への適切な接し方を学ぶことで、クレームを未然に防ぐことにもつながります。
【院内研修で押さえておきたいポイント】
- クレーム対応の流れ
- 患者への適切な接し方
- 想定されるペイシェントハラスメントの事例
- ペイシェントハラスメントにおけるパターンごとの対応方法
院内で過去に起きた事例を踏まえたケーススタディを設けると、より効果的な研修になります。大切なのは、誰が担当しても同じように対応ができるよう方法を標準化しておくことと、院内の関係者全員がその内容を理解していることです。途中で入職したスタッフにももれなく共有できるよう、定期的に研修を実施することをおすすめします。
ペイシェントハラスメントに対する取り組みを明示する
ペイシェントハラスメントへの対応マニュアルを策定し、院内の関係者に周知したら、つぎは医療機関として、ペイシェントハラスメント対策への取り組みを明確に示す必要があります。
【医療機関が実践できる主な明示の方法】
- 院内の掲示
- ホームページ
- 医療機関紹介のチラシ・パンフレット
「この病院(クリニック)ではこのような取り組みをしています」と内外に明示することで、スタッフはもちろん、通院している患者も安心して治療に専念できるようになるでしょう。また、「暴力・理不尽な要求には屈さない」というメッセージが伝われば、ペイシェントハラスメントの抑止にもつながります。
ペイシェントハラスメント対策を実践して安心できる医療現場へ
ペイシェントハラスメントは、それを受けた医療従事者の心身を脅かすのはもちろん、ひいては医療機関の経営にもかかわる深刻な問題です。やみくもに立ち向かうのではなく、医療機関としての方針をきちんと定めて対応しましょう。悪質な場合は警察への相談なども含め、毅然とした対処を行う必要があります。
医療機関に関わるすべての医療従事者や患者が安心して院内で過ごせるよう、ペイシェントハラスメント対策を実践していきましょう。