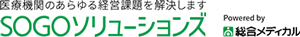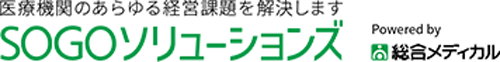コラム
医療機関におけるコスト適正化
公開日:2023/09/12
更新日:2025/07/15

はじめに
現代の医療業界では、費用上昇が深刻な問題となっています。本記事では、医療行為に直接関わるコストだけでなく、一般経費部分についても触れながら、具体的な費用項目とそれに対する対策を考察します。
医療機関の抱える6つの壁
- 比較情報不足・・・他院との比較が容易ではない
- 取引先の選択・・・サービス提供可能業者の選択肢を増やす開拓や質の検証ができない
- 適正化の手法・・・誰を相手に何をどのように適正化し、結果を最大化するか確立した手法がない
- 実績/知見・・・業界に対する知見を有した実績のあるアドバイザーが不足している
- 取引先の互恵関係・各種互恵等による取引先選定の枠が固定されている
- 担当人材不足・・・専任担当を置いて適正化を実施するスタッフがいない
一つ、二つ当てはまる部分があるのではないでしょうか?
特に「比較情報不足」はどの医療機関としても悩まれている間題であり、コストを認識する上で重要なのは過去からの改善比較ではなく、他院と比べてうちはどうなのか、がまず重要になってきます。
ここで、コスト適正化における王道ポイントについて触れさせていただきます。
王道ポイント
- 現状把握を正確に行う。
- 外部機関を積極的に利用する。
- プロジェクト責任者を必ず立てる。
- 削減目標と取組期間を経営と現場で一致させる。
- 結果をプロジェクト責任者の評価とする。
現状把握を正確に行う
最初のポイントは現在の状況を細かく把握することです。 それぞれのコスト項目における契約期間やひと月あたりの金額だけではなく、物量の過多の有無、保守であれば頻度や必要性、その取引企業様でないとダメな明確な理由など詳細を見ていく必要があります。 医療機関においては人件費割合が収益に対して 50%を超えているケースが多く「労働集約型」の傾向にあります。正確な現状把握には人件費を加味した上、コスト構造とその改善余地をそれぞれの中身まで分析する必要があります。正確に抽出したコスト適正化のポテンシャルに対して「何から実施するか」を決定します。

※医療機関における一般的なコスト構造モデル
外部機関を積極的に利用する
リアルタイムに変化するトレンドをキャッチしながら、経営に活かせるよう分析するのは却って「時間」「コスト」「無駄」の増大に繋がることを認識いただく必要があります。 院内で必ず使用されている「複合機」を例にとりお話しします。 複合機の適正化可否診断を打診すると9割方は以下のようなお返事をいただきます。 「入れ替えの度に見直しているのでうちは安いですよ?」「これ以上下げるのは無理と言われています」 入れ替える度に見直しているから安心なのか、何が根拠となってこれ以上「無理」であるのか、これらはすべて「過去の契約と比較して」の結論でしかありません。 決して院内で収集できる情報がすべてではなく、他院との比較を行い、世間一般相場と照らして「検証」することが重要であり、その観点からアウトソースをお勧めしています。
※データ分析では、他院との比較だけでなく同規模、同業種、地域などからの比較が重要になります。

プロジェクト責任者を必ず立てる
コスト適正化プロジェクトを進める責任者(担当者)を必ず決めることが重要です。 ここでその責任者の責務は「全体プロジェクトの進行把握」「各窓口の連携」となり専門知識は必ずしも必要ではないということです。 責任者を決め実施していくにしても医薬品、診療部材で言えば医師や薬剤師と、検査であれば技師長、一般経費であれば事務長との連携は必須になりますが、窓口をきめることは大きなメリットを生みます。外部機関と連携するには勿論のこと、自院で適正化プロジェクトを実施するにしても「担当者」ではなく「責任者」を立てることをお勧めしています。
削減目標と取組期間を経営と現場で一致させる
分析結果から各コスト品目の大枠の削減目標と、いつまでに何を完了させていくかを決め「経営」「現場」と双方に認識してもらうことが重要です。 順番は「経営」→「現場」です。多くの適正化失敗例で挙げられるのは経営、現場どちらにもプロジェクトとしての認識が弱く、情報集約に時間を要することになり、現場にて独断で行ったことにより削減の最大化に届かず終了となることです。各取引業者との契約タイミングにより各コスト品目における実施時期がずれてしまうことは致し方ありません。ただし、プロジェクトにて足並みを揃えることにより、以降の契約満了期を揃え、更新に向けた管理がしやすくするなどのメリットを活用すべきです。
結果をプロジェクト責任者の評価とする
プロジェクト成功の秘訣は、自己完結するにしても、外部に一部委託するにしても、責任者(担当者)にあると言っても過言ではありません。これはコスト適正化だけに言えることではありませんが、リーダーとなる人間の動きが弱ければ、取引業者(外)も院内関係部署(内)もオペレーションの最大化が図れないのは容易に想像できると思います。 ここでプロジェクト責任者が本気にならない、なれない理由として挙げられるのが「評価」です。「プロジェクト」と銘打つ限り、現行業務とは別のタスクを同時並行で完遂させるということを強く認識してもらい、その評価をしっかりと行うことが責任者を動かす原動力になります。避けたいのは「このプロジェクト含めて本来は君の仕事だ」という形では単に面倒が増えると感じる職員のほうが多数です。「面倒」という気持ちは「無難に」「早く」「形式だけ」で終わらせたい意識に直結するのです。
以上がコスト適正化を実施する上でのポイントのご紹介となります。
コスト(費用)は分解すると「数量」×「単価」です。適正な数量で発注していて適正価格で契約していれば、それは完全に「適正」であり、下げるや減らすは難しい話になります。 そこで次に適正化の手法について少し触れていきます。
有効な手法やベストなタイミングとは
どの医療機関にも多く共通して言えることは、売上減になってきた時にコスト削減に本気を出すのは本来悪手になるということです。収益が上がってきている時こそ実はベストなタイミングなのです。 取引業者(サプライヤー)からの目線としては「多く」「永く」の取引を重要視しています。 勿論、そこにはビジネスである以上「利益」も必要なため、加えて「高く」あることも要素として必要であることは否定しません。 「厳しいから協力してくれ」と「現在の健全経営を維持するためにこれからも一緒にやっていきたいので相談したい」ではどちらが本腰入れた協力体制になっていただけるかということです。
医療機関(病院)におけるコスト適正化3要素
- 委託費・・・外注検査費用、給食委託費、清掃委託費等
今までのものを今まで通り委託していると物価上昇のあおりを受けがちですが、しっかりと中身を見直すことで削減の余地があるのが委託費になります。 特に外注検査のかかわる委託費用については委託内容や院内オペレーションを大きく変えず単価の削減に成功しています。 現在の契約や単価は適正なのか?の検証をお勧めします。
- 保守費・・・エレベータ保守、空調保守、各種メンテナンス
委託費用に近い性質ですが、ビルメンテナンス全般は業界構造上、元受→実施業者までの中間マージンも多く、パっと見では適正値が掴みにくい傾向があります。中間マージンが駄目だというわけではなく、保守に対しての「適正値」を検証することをお勧めします。
- エネルギーコスト・・・電力、水道、高熱費用
近年一番ニュースにも取り上げられ、実際に高騰したあおりを経験したコスト分野です。どの電力会社も「新規獲得停止」「受入拒否」など散々だったこの2、3年でした。現在も契約単価の適正化はかなり難しく、近年注目されているのはブレーカーやデマンドコントロール、ソーラーやLEDなどの使用量に直接メスを入れるアイテムになります。
まとめ
総合メディカルでは、【現状分析を正確に行う】ことを徹底的に行います。この段階で削減の可否は70%決まるといっても過言ではありません。医療機関ごとに改善ポイントは異なります。必要に応じて外部リソースを活用して現状把握を正確に分析し、最適なコスト削減のご提案を行っています。
ぜひお気軽にご相談ください。