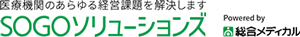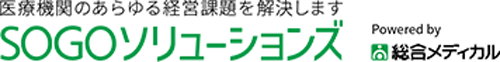コラム
災害時に医療提供を止めないために。地域の医療機関が行うべき災害対策とBCPを解説
公開日:2025/03/25
更新日:2025/09/01

近年、東日本大震災や熊本地震、そして2024年の元日に起こった能登半島地震など、地震による被害が多い日本。さらに近年、豪雨などによる水害被害も増えていることからも、医療機関における災害対策の重要性は無視できません。
地震や津波、大雨や台風などの自然災害が起きると、ライフラインが止まる可能性があります。その結果、医療供給がストップし、治療が滞る原因にもなるでしょう。
本記事では、医療機関における災害対策を解説します。有事の際にも適切な対応をとり、必要な医療を供給し続けられるよう、自院のBCP(business continuity plan: 事業継続計画)を構築しておきましょう。
医療機関におけるBCPとは
災害が起きた場合、地域の医療機関では通常診療の継続と災害対応が求められます。災害をはじめとした不足の事態が起こったときに、事業を中断させない、もしくは中断してもできるだけ短い時間で復旧させるための方針や体制、手順などを定めたものがBCPです。BCPを策定し、実践することで病院機能の損失を最小限にすることが可能です。また、早い段階で機能の立ち上げ・回復につなげることができ、被災した患者の継続的な診療が可能になります。
現在、災害拠点病院に指定されている医療機関はBCPの策定が義務化されています。また、2024年4月から、介護施設でもBCP策定が必須になりました。ただし、災害拠点病院ではなくても、被害状況によっては災害時に医療提供を行う必要が生じますし、今後BCP策定が義務化される可能性は大いにあります。できるだけ早いうちに検討を始めておくことをおすすめします。
医療機関におけるBCPの立て方
医療機関のBCPにおいて必要な視点は多岐にわたりますが、まず押さえておきたいのは主に以下の3つです。これからBCPの策定を検討するなら、これらをきちんと把握・検討しておきましょう。
BCPの基本方針を決定する
まずは災害時の理念と方針を立てることが大切です。自院の経営理念を踏まえ、たとえば以下のような基本方針を策定しましょう。これがBCPを作成する際の指針となり、この方針を達成するためにはどう動いたらよいかという考え方ができるようになります。
- 切れ目のない医療提供を行う
- 人命を最大限優先する
- 災害拠点病院として地域の医療提供の核となる
基本方針を策定したあとは、BCPを管理・実行する組織づくりを進めます。BCP策定者や実行者、進捗管理担当などを決め、BCP策定プロジェクトを立ち上げるとよいでしょう。
起こりうる被害と対応状況を想定する
自院周辺の地域性を考慮し、地震と風水害によって起こりうる被害を把握しておきましょう。たとえば海や川が近い、周囲よりも土地が低い、豪雨が起きやすいなどの立地の場合、水害による被害が想定されます。地域で策定されている洪水ハザードマップを活用し、自院周辺の被害がどのくらいになりそうかを把握しておいてください。
例:東京都の洪水ハザードマップ
東京都建設局「洪水ハザードマップ」
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/river/chusho_seibi/panhulink/hazardmap
また、地域防災計画や過去の大規模震災事例などを調査し、ライフラインが停止した場合の影響範囲も確認しておきましょう。
【平成30年7月豪雨における、ある医療機関の被害状況】
・1階天井付近まで水没
・停電、断水、固定電話不通
・予備電源は一時稼働するが、1階に設置されていたため、その後再び停電に
・CT、MRI等の医療機器が水没し故障
・駐車場に止めていた救急車両も水没
・断水でトイレが使用不可
・通信手段が携帯電話のみ、バッテリー懸念
(出典)厚生労働省「事業継続計画(BCP)策定手順と 見直しのポイント①」
また、被害が発生したときに来院する負傷者数と、出勤できる職員数を想定しておくことも大切です。公共交通機関や自家用車が使えない場合、各職員が自宅から徒歩で出勤可能か、歩いたときの到着時間目安を確認し、参集職員数を予測しておきましょう。
計画を立てる
被害想定を踏まえ、院内の各組織がいつからいつまでに何を実施するのか、計画を立てていきます。災害時には診療業務のほかに、避難や消火、ライフラインの復旧などの作業に人員が必要になります。部門別に通常業務や災害対応業務を洗い出し、非常時の優先業務を決めて、災害発生から時系列で書き出していきましょう。こうして洗い出した必要事項を文書化し、BCPとして周知・運用していくことになります。
【災害時に必要な業務の例】
- 避難誘導
- 消火・救出
- 患者の状況把握
- 院内の状況把握
- 診察・診療提供能力の把握
- ライフラインの維持・復旧作業
災害対策につながる継続的な取り組み
事業継続に向けた取り組みは、BCPを策定して終わりではありません。BCPが完成したら、訓練・教育による内容の周知、対策の進捗に関わる点検などを行い、定期的な見直しに努めましょう。
【継続的な取り組みの例】
- 訓練:BCPとして策定した業務が実行できるかを訓練によって検証する。検証する際は、医療機関の被害を想定し、近隣の機関や住民を含めて訓練を行う。
- 教育:院内研修を通し、医療機関としてどのような災害対策を行うべきかを全職員へ周知しておく。
- BCPの点検:BCPの取り組み状況を定期的に確認し、未実施の内容を上層部も含めて認識したうえで是正する。
- BCPの見直し:BCPの訓練後、責任者を中心に会議を行い、訓練の結果や社会情勢の変化を踏まえて見直しを行う。
BCPと災害対策の点検チェックリスト
自院のBCPや災害対策が必要項目を満たしているかどうか、以下のチェックリストを活用して確認してみてください。これは、経営体制や病院機能に変更があった場合などの見直しにも役立ちます。不足している点や改善すべき点がある場合は、必要に応じて検討し、見直していきましょう。
□地域における災害対応について医療機関の位置づけが明確になっている
□災害対応を審議する委員会が設立され、その位置づけが規定・明文化されている
□災害対策本部が組織され、メンバーとその役割が明確になっている
□災害時の院内外への連絡手段が整備されている
□診療継続/中止・避難の判断基準が決められ、周知されている
□災害発生後に速やかに安全が評価できる体制がある
□災害発生後に被害状況を収集・解析し、本部へ報告できる体制がある
□自家発電機能や医薬品、食料備蓄など、ライフライン確保の手段が整っている
□緊急地震速報と連動したシステムが整備されている
□災害時の人員確保のための体制が整備されている
□災害時の診療体制が規定され、周知されている
□電子カルテシステムが使用できない場合の対策がなされている
□マスコミ対応・広報(患者の情報公開)の方法が検討されている
□外部の医療チーム・医療ボランティアの受け入れ体制が整備されている
□災害訓練を行っている
□災害時の対応マニュアルが整備されている
(参考)石川県「BCPの考え方に基づいた病院災害対応計画作成の手引き」https://www.pref.ishikawa.lg.jp/iryou/documents/bpctebiki.pdf
BCPを策定して万全な災害対策を
地震や津波、台風、水害などの災害は、いつどこで起こってもおかしくありません。いざというときに慌てることのないよう、BCPを策定し、医療機関としてどのように対応するかを検討し、示しておくことが重要です。
地域の医療機関として求められるのは、有事の際でも患者に対して切れ目のない医療を提供することです。そのために必要なのは、院内の関係者が自分の役割を理解し、すぐに動けるようにしておくこと。BCPを策定して満足するのではなく、それを周知・運用し、適宜見直しをしながら、不足の事態に備えておきましょう。
医療機関向け 自然災害BCP策定支援の資料ダウンロード
地震や台風など、頻発する自然災害が発生した際に、患者さまやスタッフの皆さまを守り、一刻も早く病院機能を復旧させるためのBCP策定をお手伝いいたします。