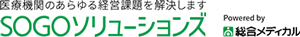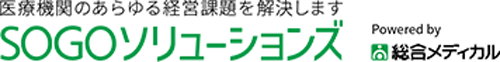事例紹介
「選択と集中」で地域医療を支える病院が医薬品管理の負担を軽減して業務を効率化
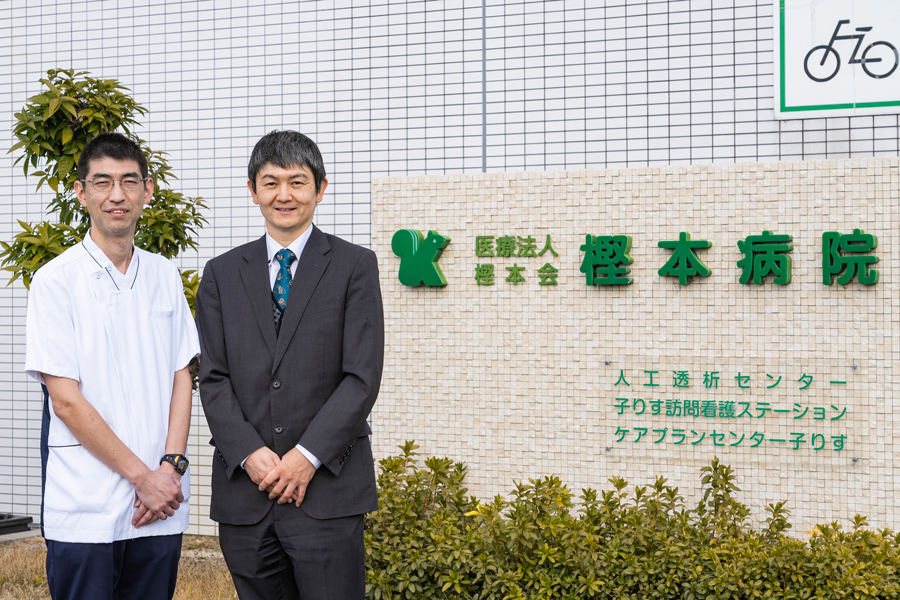
医療法人樫本会 樫本病院
所在地:大阪府大阪狭山市東茱萸木4-1151
電話:072-366-1818
URL:https://kashimoto.or.jp/
病床数:199床
診療科目:整形外科、内科、外科、腫瘍内科・緩和ケア内科、泌尿器科、循環器内科、脳神経外科、神経内科、眼科、乳腺外科、形成外科、皮膚科、麻酔科、リハビリテーション科、関節外科、リウマチ科、肛門外科、消化器内科、消化器外科
課題
- 医薬品卸4社との個別価格交渉に手間がかかっていた
- 年1回に変更された薬価改定への対応が負担となっていた
- 約700品目の医薬品の価格交渉にかかる負担が大きかった
- 院外処方になり薬剤購入が減少した中で交渉業務の負担が増えていた
- スキルが求められる価格交渉に不安を感じていた
- これまでの医薬品購買体制を大きく変えずに業務改善したかった
- 薬価差益を意識して医療法人の経営にさらに貢献したいという思いがあった
解決策
- 総合メディカルのGPOサービスを導入し、4社との個別交渉から一括管理へ移行した
- 「SMart-Web」を活用して新規採用薬の最安卸を効率的に決定するようにした
- 薬剤師や事務長の業務負担を軽減し、本来業務に集中できる環境を構築した
- 地域の医薬品卸との関係性を維持しながら、コスト削減と業務効率化を両立した
効果
- 価格交渉の手間が大幅に削減され、業務負担が軽減された
- 請求書が複数社から一社にまとまり、事務処理が効率化された
- 新規採用薬剤の最安卸が1週間程度で決定できるようになった
- 毎月の納品実績データが提供され、コスト管理が容易になった
- 医薬品卸との関係性が大きく変わることなく、円滑な取引が継続できた
- 本来業務に時間を割けるようになった
地域医療の拠点として40年以上にわたり市民の健康をサポートする病院

左:薬局長 高橋 様 右:事務長 酒谷 様
――はじめに「樫本病院」がどのような病院か教えてください。
酒谷 様(以下、酒谷):
樫本病院は、大阪府の南河内エリア、大阪狭山市に位置する199床の医療施設です。昭和57年に有床診療所を開設して以来40数年にわたり、市民病院のない人口5万人台の自治体の地域医療を支えてきました。
昭和の終わりから平成中期までの初代理事長の時代は、検診や未病の段階から重症ターミナルまで幅広い医療提供をおこなうことに主眼を置いていました。二代目の樫本秀好理事長になってからは、より専門性を高めることにも重点を置くようになり、整形外科を中心とした回復リハビリテーション病棟や手術室の拡張、そしてがんの緩和ケア病棟の開設などを進めています。また、眼科の白内障手術等も積極的におこなっています。
当院では、地域の医療ニーズに応えるべく、「選択と集中」の考え方で新しい施設基準も積極的に導入しています。令和6年11月からは地域包括医療病棟もスタートさせました。199床の規模をフル活用して地域医療をサポートする運営をおこなっております。
負担が増え続けていた薬価交渉と環境変化への対応を考慮してGPOサービスの導入を検討

――総合メディカルの「医薬品共同購買(以下GPO)」を利用される前はどのような状況だったのでしょうか?
酒谷:
当院は4社の医薬品卸と取引をしています。毎年の交渉業務にはかなり手間がかかっていました。
また、外来処方を院内で調剤していたときは、薬剤購入費も多く積極的に取り組んでいましたが、院外処方になってからは、交渉が単なる業務負担に感じられるようになっていました。そのタイミングで他社から医薬品共同購買の話があり、そこで初めてGPOというスキームがあることを知りました。ただ、その提案内容は当院にとって制約が多く、メリットが少ないと考え導入には至りませんでした。
その後、他院の事務長から総合メディカルのGPOサービスを紹介されました。信頼できる方からの紹介だったこともあり、話を聞いてみることにしました。その結果、総合メディカルからの提案内容はデメリットが極めて少なくメリットが多いと感じられたため、導入を検討し始めました。

――それまで薬剤の価格交渉やデータ管理はどのようにされていたのでしょうか?
高橋 様(以下、高橋):
当院では約700品目の医薬品を取り扱っており、データ管理は薬局でおこなっていました。
酒谷:
当院の薬価交渉は事務長の仕事という位置付けでした。700品目すべてを個別に交渉するということではなく、全体と捉えて調整するような形で進めており、またこちらの知識も十分ではないため、正直なところ強い交渉力を発揮できていたかは疑問だと考えています。
また、薬価交渉の業務は常時おこなうものではないため、プラスアルファの業務負担と感じていました。以前は2年に1回、秋ごろに「そろそろだな…」と腰を上げ、10月から1月にかけて各医薬品卸と2〜3回の打ち合わせをして価格を決めていました。薬価改定が年1回になってからは、率直なところ「もう勘弁してください」という気持ちになっていたのは確かですね。
ちょうどそのころ、薬局長と私は次世代への引き継ぎを考え始める年齢に達していました。その中で薬価交渉のような専門的で負担の大きい業務を次の担当に引き継ぐことに不安を感じ、躊躇していました。このような背景もあり、薬価交渉の負担を軽減できる方法を探していました。
決め手になったのは「自由度」と「柔軟性」の高さ

――総合メディカルのGPOサービスを検討する際、その他のサービスと比較検討はされましたか?
酒谷:
比較しました。先ほどお話した他社の医薬品共同購買と比較検討しています。まず、比較したサービスでは取り引きできる医薬品卸が限定されており、当院の運用に適さない部分があると感じました。また、削減された費用の一部を共同購買会社に支払う必要もありました。
一方、総合メディカルのGPOサービスは、すでに医薬品卸としての機能があり、そのスキームに乗る形でした。特別なインセンティブを支払う必要もなく、元々付き合いがあった地域の医薬品卸との取り引き関係を維持しながら導入できるという柔軟性もありました。
比較検討をおこない、手数料やその他の制限を検討して総合的に見ると、私たちには総合メディカルのGPOサービスの提案が合っていると判断できました。
さらに、万が一GPOサービスの利用をやめた場合でも、違約金なしでスムーズに元の医薬品購入の仕組みに戻せると確認できました。このように、導入にあたってのリスクが極めて小さい点も決め手の一つでした。そして実際に、提示された医薬品の価格はこれまでの交渉よりも明らかに良い条件となっていました。
当院には、新しい取り組みを積極的に取り入れる風土があります。院長にGPOサービスの導入について説明したところ「事務側としては絶対変えたほうがいいと思っているの?」と聞かれ、「もちろんです」と答えると「それならやってみたら」と言ってもらえました。その後、総合メディカルの担当者から「最速の決断かもしれません」と言われるほど、すぐに導入が決まりました。この決断が結果として病院の業務効率の向上や収益改善につながることになり、2024年度の予算にも反映されました。
導入後、数値でも体感でもすぐに効果が実感できた

――GPOサービスを導入されて、効果をどのようにお感じになっておられますか?
酒谷:
GPOサービスの導入後、最初に実感したのは請求書が4社から1社になって事務処理がシンプルになったことです。これまで各医薬品卸からの請求を一つひとつ確認していましたが、その作業が1回になりました。また、数字的にもメリットがあることを確認しています。発注方法は変わりませんし、各医薬品卸との関係性も悪化することなく良好に維持できています。
高橋:
薬局としては、担当の医薬品卸を決めたあとはこれまでと全く変わらず、いつも通り発注できています。変化を感じたのは新規採用薬の医薬品卸の決定プロセスです。以前は相見積もりを取るのに手間がかかっていましたが、今では「SMart-Web※」で依頼すれば1週間程度で最安値の医薬品卸を教えてもらえるので、非常に便利になりました。
※「SMart-Web」とは
検索して品目を選択するだけで見積依頼ができるWebシステム(利用料無料/インターネットの繋がるPCで利用可能)
酒谷:
薬局では薬剤師が病棟業務を増やしていく中、このようなバックオフィス業務の負担が減ったことは大きいと考えています。最近は薬の出荷調整など供給不安の問題の対応にも時間を割けるようになりました。
そのほか、毎月納品実績のデータを送ってもらえるため、値引き率も把握しやすくなりました。これまではそのようなデータを各医薬品卸から取得するのが難しかったのですが、今は振り返りや分析をおこないやすくなっています。データベースがあるため、年度末の棚卸し作業も効率化でき楽になりそうです。
GPOサービスは業務効率と経営の質を高めてくれる

――今後、総合メディカルのGPOサービスに期待していることを教えてください。
酒谷:
今後、総合メディカルのGPOサービスに多くの医療機関が参加することで、私たちの購入コストがさらに下がることを期待しています。多くの病院が参加し注目を浴びるようになれば、それだけ価格交渉力が高まるのではないでしょうか。
高橋:
現在、GPOのシステムの改修作業が進んでいると聞いていますが、後発医薬品で複数社から出ている場合の選択に関する情報が増えたり、供給が安定している製品が事前に分かったりするようになれば助かると思っています。
GPOサービスを検討している病院の方々にお伝えしたいポイントは、全ての品目において最安卸で絶対に購買しなければならないという固定観念を持たないことだと思います。あくまで推奨であり、実際の発注権は病院側にあります。今のような医薬品の供給不安の時代では、最安値の医薬品卸に在庫がないこともあります。その場合は他の医薬品卸から購入でき、柔軟に選択できることが総合メディカルGPOサービスのメリットの一つではないかと感じています。
酒谷:
同感です。柔軟に運用することが大切だと思います。特に近年の医薬品における供給問題を踏まえ、現場の薬局に負担をかけないように配慮することが大切です。私はGPOサービスの良さを地域の事務長会でも伝えています。コストが下がり業務効率も良くなるメリットがあるので、地域の医療機関にも広がってほしいと期待しています。